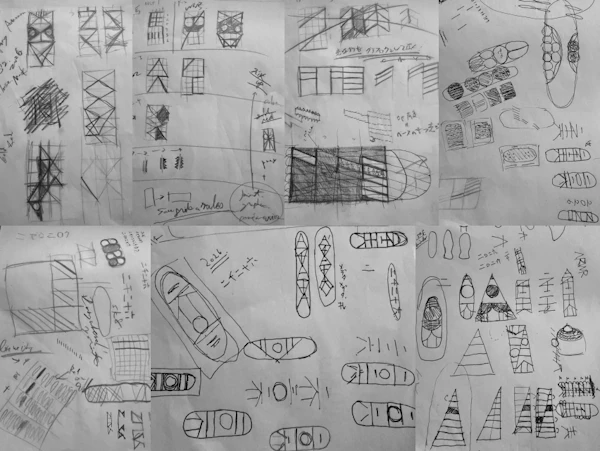雪で鉄道が止まる理由、止めないための工夫

目次
夜中にカップ焼きそばを食べたりしたいです。
この記事は、社内イベント「お茶会」での発表内容をもとにまとめたものです。
今回は弊社の wataru が鉄道と雪の関係について話しました。
東京ではあまり雪が降るイメージがありませんが、日本全国には冬になるとまとまった降雪に見舞われる地域がたくさんあります。
そして、雪といえば交通機関の麻痺。高速道路の通行止めや飛行機の欠航などが話題になりますが、鉄道も例外ではありません。
では、なぜ鉄道は雪に弱いのでしょうか?
結論から言えば、鉄道という仕組み自体が「雪と非常に相性が悪い」構造になっているためです。
雪が降ることで発生する主な問題には、以下のようなものがあります。
- ブレーキが効きづらくなる
- 線路が雪に埋まって走行できなくなる
- 列車が雪崩に巻き込まれる危険性
- ポイント(分岐器)が雪で動かなくなる
- 車体から落ちた雪が周囲に被害を及ぼす
- 車両の機械部分が凍結する
これらの問題について、次章からひとつずつ詳しく見ていきましょう。
01 鉄道が雪に弱い理由
ブレーキが効きづらい
鉄道車両は、鉄のレール上で車輪を転がすことで動いています。
車輪は固い鉄製であるため、レールと接触する面が小さく、摩擦も少ないのが特徴です。
摩擦が小さいことで、少ない力で動かせる上に、転がる運動に対する抵抗も小さいというメリットがあり、現在の鉄道は時速300キロを超えるような高速運転も可能となっています。
一方で、動き出そうとする力や、停めようとする力を生み出す摩擦が作りづらい点は大きな弱点です。
雪が車輪に噛みこむと摩擦力がさらに小さくなり、車輪の空転や滑走が増えてしまいます。
実際、2014年の大雪の影響で、東急東横線・元住吉駅では電車が止まりきれず、衝突事故が発生しました。
雪で線路が埋まり走れなくなる

特に豪雪地帯では、わずか 1 時間で地面が見えなくなるほどの雪が降ることもあります。
数メートルもの積雪によって、線路や鉄道設備がすっかり埋もれ、列車は走れなくなります。
こうなると、除雪が完了するまで列車は駅で立ち往生。
乗客もその場で待機するか、ほかの交通手段を使って移動するしかありません。
たとえば昭和38年の豪雪では、北陸地方に記録的な雪が降り、除雪作業は10日間にもおよびました。
国鉄職員に加えて自衛隊や地元の人々も参加し、総出で雪を掻き出す日々が続いたといいます。
列車が雪崩に巻き込まれる可能性
山間部の豪雪地帯では、雪崩が起きるおそれがあります。
走行中の列車が巻き込まれると、大事故につながりかねません。
実際に、過去にはそうした事例もありました。米坂線や北陸線で発生した事故が、その代表例です。
このような背景から、山を越える路線では雪が降るたびに運休や速度規制が行われることが少なくありません。
ポイントが凍結する
都市部でも雪が降ると、空転や滑走に加えてポイントの不具合が発生します。
ポイントとは、列車の進行方向を切り替えるための装置です。
降り積もった雪がポイントの隙間に詰まると、動かせなくなることがあります。
また、操作用の機械が凍結し、切り替えができなくなるケースも見られます。
このような状況になると、運行の継続は困難で、結果として、列車の遅延や運休が発生します。
車体から剥がれた雪の影響
かつて東海道新幹線では、関ヶ原周辺の雪によって思わぬ問題が発生していました。
雪の多い区間を走行した後、車体に付着していた雪の塊が落下し、線路のバラストを跳ね上げてしまうのです。
跳ねたバラストは、車両の走行機器や車体、さらには窓ガラスにまで損傷を与えることがありました。
沿線の民家へ飛び散るといった被害も報告されています。
現在ではスプリンクラーによって雪を溶かす設備が導入されましたが、関ヶ原付近では冬の間、列車が徐行運転を強いられることもあります。
02 雪とどう戦うか
雪への対策は、主に3つの方針に分けられます。
- 雪を取り除く
- 雪に強い路線を作る
- 雪に強い車両を使う
どれも現場で積み重ねられてきた工夫ばかりです。
雪を取り除く

もっとも基本的な対策は、雪を取り除くことです。
専用の除雪車で線路の雪を脇へ押し出したり、場所によってはスコップや除雪機を使った手作業も行われます。スプリンクラーなどの設備がない区間では、人力での対応が欠かせません。
除雪車にはいくつかの種類があり、「ラッセル式」は車体前部の大きな翼で雪を左右に押しのける構造です。一方で、「ロータリー式」は回転する刃で雪を巻き込み、遠くに飛ばして排雪する仕組みとなっており、より深い積雪にも対応可能です。
近年では、駅構内にポンプ式や小型ロータリー除雪機を導入するケースも増え、少人数でも効率よく作業が進められるようになっています。
雪に強い路線を作る
比較的新しい路線では、雪による影響を最小限に抑えるための設計が積極的に取り入れられています。
単に除雪するだけでなく、そもそも積もりにくくする・積もっても機能を維持できる構造にするという考え方です。
ここでは、そうした設備や工夫のいくつかを紹介します。
スプリンクラー

スプリンクラーは、常に水を撒いて雪を溶かし流すための設備です。特にトンネル付近では、湧水の排水も兼ねて使われることが多く、新幹線では雪が舞い上がるのを防ぐ目的でも活用されています。
水の散布量は非常に多く、大雨が降り続いたときと同程度の水が発生する場合もあり、線路や高架橋には優れた排水性能が求められます。排水機能が不十分だと、土壌の緩みによって地盤が不安定になるおそれもあるため、設置には地形や構造を踏まえた慎重な判断が必要です。
消雪パネル・ジェット噴射によるポイント融雪
除雪車では対応が難しい場所では、地面に設置された設備によって雪を溶かす方法が採用されています。そのひとつが「消雪パネル」です。これは温水などを循環させることで、線路やポイント周辺の雪を直接溶かします。
住宅街や高速道路を跨ぐ高架橋の上など、物理的に雪をどけられない場所で使われることが多く、雪処理の手間を大幅に軽減する仕組みといえるでしょう。
また、分岐器(ポイント)の切り替えが重要な駅構内などでは、温水をジェット噴射する装置を使ってポイントの隙間に詰まった雪を吹き飛ばす方式もあります。これにより、雪による機構の凍結や動作不良を防ぐことができ、列車の運行を安定させるうえで大きな効果を発揮しています。
他の手段としてカンテラ(ランプ)を使用する方法もあります。線路の周囲に火を灯すことで、ポイントまわりの雪を直接溶かすというものです。電気式の装置が整備されていない場所などでは、降雪後に臨時で設置されることがあります。
雪に強い高架橋
豪雪地帯では、積雪による運行支障を防ぐため、構造そのものにさまざまな対策が施されています。以下は代表的な例です。
- 貯雪型高架橋
- 比較的降雪量が少ない区間では、線路脇の溝に雪を一時的にためておき、自然に融かすか、融雪パネルを利用して処理する
- 流雪溝
- 事前に大量の水を流しておき、積もる前の雪を押し流す方式。水資源が豊富な地域で導入されている
- 開床式高架橋
- 線路下が開放されている構造で、自然と雪が落ちる仕組み。除雪の手間を軽減するうえで有効
構造段階から雪対策を組み込むことで、運行の安定性が大きく向上しています。
長大トンネルによる雪対策

豪雪地帯を通る鉄道路線では、線路自体を雪の届かない場所に逃がす「長大トンネル」が有効な手段となっています。
とくに山間部では、地表に線路を通すと雪崩や吹き溜まりのリスクが高くなります。そこで、線路自体を山の内部に通すことで、雪の影響を受けない空間に列車を通す構造が選ばれてきました。
トンネル内は冬でも外気より温度が高く、風雪の影響を受けにくいため、除雪の必要もほとんどありません。結果として、運行の安定性を保ちやすくなります。
たとえば、上越新幹線の越後湯沢〜長岡間では、長大トンネルとスノーシェッド(雪覆い)を連続して配置することで、「屋根のない区間」をほぼ無くしています。これにより、積雪そのものを構造的に回避し、冬でもスムーズな運行を実現しています。
雪を遮る構造物

山間部や風が強い地域では、線路が雪に埋もれたり吹き溜まりになるのを防ぐために、周囲を囲ったり屋根をかけたりする設備が用いられています。
- スノーシェッド(雪覆い)
トンネルのように見える構造物で、線路の上に屋根をかけて雪の直撃を避けます。特に斜面の下や橋の部分など、雪崩や吹き溜まりが発生しやすい場所に設置されている - 防雪柵
雪が風で運ばれてくるのを防ぐため、線路の周囲に設置される柵です。雪が柵の向こう側で自然に落ちるよう設計されており、視界が悪化するのも防げる - 防雪林
人工的に植えられた樹木の列で、吹き付ける風と雪を弱める役割を担います。自然環境に調和しながら、雪の被害を和らげる方法
これらの設備によって、線路そのものに雪が届くのを防ぎ、除雪の必要性を抑えると同時に、事故や運休を未然に防ぐ仕組みが整えられています。
雪に強い車両を作る
鉄道の安定運行には、線路だけでなく車両側の備えも重要です。特に寒冷地では、積雪や凍結による支障を防ぐため、さまざまな対策が施されています。
- 耐雪ブレーキ
- 降雪時には、スイッチで耐雪モードに切り替えることで、車輪とブレーキシューの隙間をなくし、雪が噛みこむのを防ぐ構造。これにより、制動力の低下やブレーキ不良を防ぎます。寒冷地向け車両だけでなく、首都圏のE233系やTX-3000系などにも採用されている
- スノープラウ(排雪板)
- 先頭車両に装着され、進行方向に積もった雪を線路脇へ押しのけながら走行する。軽度の積雪であれば、これだけで運行を続けることが可能
- ヒーターによる凍結防止
- ドア周辺や台車の一部にはヒーターが設けられ、氷や雪の付着を抑えている。秋田などの地域では、ドア下に「高温注意」のステッカーが貼られている例も見られ、乗客への配慮もされている
03 まとめ
雪は、美しい一方で鉄道にとっては厄介な存在です。視界を奪い、進行を妨げ、時には重大な事故を引き起こすこともあります。
それでも私たちは、雪と共にある地域で、安全かつ安定した鉄道運行を目指してきました。スプリンクラーや除雪装置、雪に強い車両、そして長大トンネルの整備に至るまで、各地でさまざまな対策が実践されています。
そして、万全の備えをしていてもなお、雪の影響を完全に排除することはできません。だからこそ、運休や遅延を前提にした仕組みを整えることも、現代の鉄道には求められています。
列車がいつも通りに走る、その当たり前の裏側には、雪と向き合い続ける技術と知恵の積み重ねがあるのです。
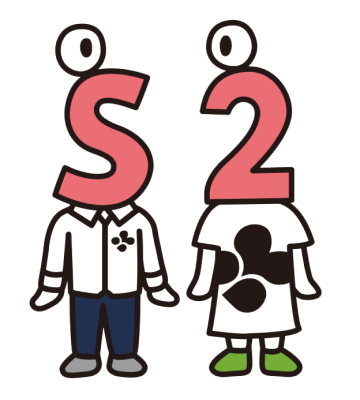
S2ファクトリー株式会社
様々な分野のスペシャリストが集まり、Webサイトやスマートフォンアプリの企画・設計から制作、システム開発、インフラ構築・運用などの業務を行っているウェブ制作会社です。
実績
案件のご依頼、ご相談、その他ご質問はこちらからお問い合わせください。